不動産の「表示に関する登記」における専門家、土地家屋調査士。
土地家屋調査士しかできない独占業務を活かして、独立・開業を夢見る方も多いのではないでしょうか?
世間では、土地家屋調査士はやめとけと言われることもあり、「これから土地家屋調査士になろうと思っていたのに…」「土地家屋調査士への就職に向けて今から準備しようと思っていたけどやめた方がいいのかな」と不安に感じている人もいるかもしれません。
そこで今回は土地家屋調査士はやめとけと言われる理由や、どんな人が土地家屋調査士に向いているのかについてご紹介していきたいと思います!

土地家屋調査士がやめとけと言われる理由やどんな人が活躍しているのか知りたい!



土地家屋調査士になろうか迷っている方は是非参考にしてみてください。
土地家屋調査士のメリットはたくさんある!
そもそも土地家屋調査士になるとどんなメリットがあるのでしょうか?
土地家屋調査士で実際に働いている方の例を参考にどのような良いことがあるのかを一緒に見ていきましょう!



実際に土地家屋調査士で働いている人がどのような点にメリットを感じているかは貴重な情報になりそうです!



就職を考えている人にとっては是非とも知りたい情報ですね。
様々な場所へ行き、多種多様な人々と関わることができる
メリットの1つ目は「様々な場所へ行き、多種多様な人々と関わることができる」ということです。
土地家屋調査士の仕事は地元に根付いたものが多いですが、案件によっては遠方まで出向くこともあります。
また、境界線を確認していく過程では、隣地の所有者や役所の担当者など、依頼地に接する土地・道路に関わる全ての利害関係人と話をする必要があります。
色々な土地で、色々な人と出会うので、毎回新鮮な気持ちで取り組むことができるでしょう!



土地家屋調査士にも出張があるんですね。



ベテラン土地家屋調査士の中には、遠方で仕事を終えた後、現地で旅行を楽しむという方もいるみたいです!
AIに奪われにくい仕事内容で将来性がある
メリットの2つ目は「AIに奪われにくい仕事内容で将来性がある」ということです。
実際に、大規模測量においては、ドローンや3Dスキャナーなどの新技術が導入され始めているところもあります。
しかし、個人的な敷地などの狭い範囲の測量では、まだまだ職人の経験に基づいた技術に頼る部分が大きいです。
また、立会で揉め事が発生した際の解決には、相手に気持ちを考え、その場の空気を読んで対応するといった「人ならではのコミュニケーション」が必要となってきます。
AIが完全に代替できる仕事とは言い難く、土地家屋調査士はこれからも残っていく仕事と考えて良いでしょう。



将来を見据えて、土地家屋調査士に求められる能力は多そうですね。



最近は外国籍の依頼者も増えているので、語学力もあると他の土地家屋調査士と差別化できるでしょう!
今後の仕事数の増加が見込まれる
メリットの3つ目は「今後の仕事数の増加が見込まれる」ということです。
高齢化が進んでいる日本では、土地の放棄や相続に伴う土地の分割・売買が増加すると予想されます。
2024年に相続登記が義務化されたことも要因となり、今後、土地家屋調査士の仕事は増加してくるでしょう!
今後もしばらくはこの流れが続くと予想されており、長い目で見ても安定した仕事量が見込まれます。



土地家屋調査士の仕事に将来性はあるのかな?



土地家屋調査士の半数以上は60~80代であり、世代交代に向けて若い世代の需要が高まっているので、将来性のある仕事と言えるでしょう!
土地家屋調査士はやめとけと言われる理由7選
土地家屋調査士は8士業の1つとして知られており、将来性がある仕事にも関わらず、「土地家屋調査士はやめとけ」と言われることがあります。
土地家屋調査士になりたいと思っていた方にとっては、とても不安になる情報ですよね。
なぜ土地家屋調査士はやめとけと言われるのかについて、世間で言われている理由を見ていきましょう!



土地や建物のプロフェッショナルと言っても過言ではないのに、なぜ「土地家屋調査士はやめとけ」と言われているんだろう?



それにはいくつか理由があるので一緒に見ていきましょう。
体力的にきついから
やめとけと言われる理由の1つ目としては「体力的にきついから」というものです。
土地家屋調査士の大事な仕事は、屋外での測量です。
夏は炎天下の下で、冬は極寒の中で作業しなければならないことも少なくありません。
遠方の依頼があれば、長時間、車を運転する技術も必要になります。
過酷な作業環境での仕事が中心になることから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



体力に自信がないから、土地家屋調査士には向いていないのかな?



「体を動かすことに慣れれば気にならなかった」という人もいるので、一概に向いていないとは言い切れません!
繁忙期がとてつもなく忙しいから
やめとけと言われる理由の2つ目としては「繁忙期がとてつもなく忙しいから」というものです。
土地家屋調査士の繁忙期は、1月~3月と言われています。
年度末ということもあり、企業や地方自治体からの依頼・締め切りが何個も同時に重なる傾向があります。
大型案件は規模が数百万円と大きく、同時進行で進めるには体力と気力が必要になってきます。
繁忙期に抱える仕事のプレッシャーが非常に大きいことから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



繁忙期以外は、どれくらいの忙しさなのかな?



勤務地にもよりますが、閑散期は「繁忙期とのギャップがありすぎる!」と言われるくらい落ち着くようなので、毎日忙しさが続くということは無さそうです。
常に勉強が必要だから
やめとけと言われる理由の3つ目としては「常に勉強が必要だから」というものです。
不動産登記法や測量法などの法規は頻繁に改正されるので、常に最新の法改正情報を把握している必要があります。
また、測量などで使用する機材が新しく導入される度に、マニュアルを読み込み、操作に慣れていかなければなりません。
日々知識を更新するために勉強し続けなければならないことから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



定期的に勉強会などは開かれているのかな?



試験合格後に入会する「土地家屋調査士会」が研修を開くことがあるので、申し込みをすれば参加できるよ。
人間関係のストレスが多いから
やめとけと言われる理由の4つ目としては「人間関係のストレスが多いから」というものです。
土地家屋調査士の仕事で、人との関わりは欠かせません。
無茶ぶりをしてくる依頼者や、立会結果に納得がいかず暴言を吐いてくる隣地所有者とも交渉していかなければなりません。
やりがいと同時に人間関係でのストレスも多いことから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



自身の財産・利益がかかっているので、依頼人や関係者の人も熱が入ってしまうのでしょうね…



厳しい局面を潜り抜けて難しい案件を無事解決し、依頼人に感謝された時の達成感・やりがいはひとしおです!
不規則な勤務形態だから
やめとけと言われる理由の5つ目としては「不規則な勤務形態だから」というものです。
境界線の立ち合いでは、依頼者の方も平日は仕事をしている人が多いので、必然的に土日の希望が多くなります。
悪天候で作業が延期になった場合は、締切に間に合わせるために、休日を返上して勤務が必要になる時もあります。
カレンダー通りに休める仕事ではないことから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



事務所として、何か対策はされていないのでしょうか?



事務所によっては、交代で土日休みを取得したり、平日に振替休日を取得するようにしたりと勤務形態を整えようとしているところもありますよ!
資格取得から独り立ちまで時間がかかるから
やめとけと言われる理由の6つ目としては「資格取得から独り立ちまで時間がかかるから」というものです。
土地家屋調査士の試験は年に1回しか実施されず、合格率は10%という難関国家資格です。
無事資格を取得しても、実務で経験を積むには短くて1年、長くて5年ほどかかることもあります。
仕事が軌道に乗るまでに時間を要することから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



どうせ資格を取得するならコストパフォーマンスが気になります…



税理士、司法書士など他の士業に比べて取得しやすい資格のわりに、土地家屋調査士を目指す人は少ないので、コストパフォーマンスは抜群です!
年収のバラつきがあるから
やめとけと言われる理由の7つ目としては「年収のバラつきがあるから」というものです。
土地家屋調査士の年収は、案件が多い都市部では高く、案件が少ない地方部では低くなる傾向があります。
また、独立しているか、会社に雇用されているか、勤務形態によっても差が出てきます。
地域や勤務形態によって年収の高低差が激しいことから土地家屋調査士はやめとけと言われているのです。



具体的に年収はどれくらいなのでしょうか?



土地家屋調査士の年収は400~500万円と言われていますが、中には年収1000万円越えの人もいます!
土地家屋調査士をやめた人の理由
土地家屋調査士はやめとけと言われていることもあり、やはり中には実際にやめた人もいることは事実です。
土地家屋調査士として働いていた人がどういった理由でやめていったのかも合わせて見ていきましょう!



実際にやめた人の声を知ることで教訓になりそうですね…



リアルな事情を知ることができるので、参考にしてください。
体調を崩したから
土地家屋調査士をやめた人の理由の1つ目として「体調を崩した」というものがあります。
屋外での作業が多かったり、不規則な勤務形態だったりで、疲労が溜まり体調を崩すというのは想像に容易いでしょう。
古い慣習が残ったままのブラック事務所も存在し、労働環境に疲弊してしまい辞めてしまった人もいるようです。



ブラック事務所を避けるには何ができるのでしょうか?



入職後のトラブルを防ぐためにも、雇用時に労働条件通知書を必ず受け取るようにしましょう!
人間関係に疲れたから
土地家屋調査士をやめた人の理由の2つ目として「人間関係に疲れた」というものがあります。
土地家屋調査士は、仕事上人と関わることが多いので、その分トラブルに出会うことも多いです。
立会結果に納得のいかない隣地所有者から暴言を吐かれることもあり、それが積もり積もって辞めてしまう人もいるようです。



依頼者、隣地関係者、同業者、同僚と関わる人々が多種多様なので、それぞれの要望に全て応えるのは相当難しそうですね…



困った時には、同業者同士で助け合って情報交換することもあるそうなので、横のつながりを大事にしておくと良さそうです!
廃業せざるを得なくなったから
土地家屋調査士をやめた人の理由の3つ目として「廃業せざるを得なくなった」というものがあります。
事務所を構えるには、物件代や機材代、人件費などかなり高額なコストが発生します。
立地を誤ったり、人脈が上手く築けなかったりして案件が少ないと、資金運用が出来ずに廃業せざるを得ない人もいるようです。



土地家屋調査士の廃業率はいくらなのでしょうか?



土地家屋調査士の廃業率は約3%で、日本全体の廃業率は3~5%なので、ほぼ同じ水準かやや低い水準です。
土地家屋調査士に向いていないのは偶然の可能性も
土地家屋調査士はやめとけと言われてることや、実際に辞めてしまった人もいることは事実ですが、深く心配する必要はありません。
その人たちがたまたま向いてなかったという可能性も大いに考えられるからです。
ここでは実際にどのような人が土地家屋調査になるのをやめておくべきなのか、向いていないのかを確認していきましょう!



土地家屋調査士に向いていない人はどんな特徴があるんだろう?



土地家屋調査士は肉体労働も頭脳労働も行うので中には向いていない人もいます。
屋外での作業に抵抗がある
土地家屋調査士に向いていない人の特徴1つ目は「屋外での作業に抵抗がある」です。
土地家屋調査士の仕事は、現地調査や測量など、屋外での作業が欠かせません。
デスクワークを中心とした働き方を望む人は、思うような働き方が出来ずストレスを感じる原因になるかもしれません。
室内で完結する業務だけを担当することは難しいので、屋外での作業に抵抗がある人は土地家屋調査士に向いていないと言えるでしょう。



どうしても室内だけで働くことは難しいのでしょうか?



配属次第になりますが、大きい事務所では業務分担されているところもあります。決して多いとは言えませんが、書類作成専門で働いている人も存在します!
細かい作業が苦手で大雑把
土地家屋調査士に向いていない人の特徴2つ目は「細かい作業が苦手で大雑把」です。
土地家屋調査士の主要な仕事である測量や作図などでは、ケアレスミスが許されず、正確な作業が求められます。
また、トラブルを防ぐためには、依頼者や関係者との綿密なコミュニケーションも不可欠です。
全体を通して丁寧に物事を進めることが必要なので、細かい作業が苦手で大雑把な人は土地家屋調査士に向いていないと言えるでしょう。



適当な人に自分の大切な土地を任せるのは不安ですからね…



自分の仕事に責任を持って取り組んでくれる人に依頼したいですよね!
スケジュール管理が苦手
土地家屋調査士に向いていない人の特徴3つ目は「スケジュール管理が苦手」です。
土地家屋調査士の仕事は、天候や他者の都合で予定変更が生じることが少なからずあります。
常に複数の案件を抱えて同時進行で捌きつつ、突発的な予定変更に対応していかなければなりません。
効率的・計画的に仕事を進めるために時間を調整する能力が求められるので、スケジュール管理が苦手な人は土地家屋調査士に向いていないと言えるでしょう。



時間の使い方に自信がないのですが、何か良い方法はありますか?



最近は、案件・スケジュール管理システムが導入されている職場もあるので、上手く活用していきましょう。
土地家屋調査士に向いている人は実はたくさんいる
土地家屋調査士が向いていない人がいることも事実ですが、最低限3つの特徴を持っていれば、土地家屋調査士として活躍していくことは全然可能です。
何も特別なスキルや性格が必要ではありませんので、以下の特徴に当てはまっているあなたは心配せず自信を持って土地家屋調査士になるための準備を進めていきましょう!
- フィールドワークに抵抗のない人
- コミュニケーション能力が高い人
- 文系科目・理系科目の両方の知識がある人
土地家屋調査士になることを考えている人は是非参考にしてみてください。



自分が土地家屋調査士に向いているかどうか特徴が知りたい!



就職する際に自身に適性がありそうかどうか確かめていきましょう。
フィールドワークに抵抗のない人
土地家屋調査士に向いている人の特徴の1つ目は「フィールドワークに抵抗のない人」というものです。
土地家屋調査士の仕事では、基本的には外勤も内勤も両方行います。
デスクワークだけでなく、外出をしてリフレッシュしながら仕事に取り組みたい人には向いているでしょう。



フィールドワークとはどういう意味ですか?



野外など現地での調査や研究という意味があります。土地家屋調査士の仕事では、現地の状況調査や測量などがフィールドワークに含まれます。
コミュニケーション能力が高い人
土地家屋調査士に向いている人の特徴の1つ目は「コミュニケーション能力が高い人」というものです。
何度も繰り返しますが、土地家屋調査士は、人との関わりが多い職業です。
案件を円満に終結させるために、関係者全般と良い関係性を築けるように努め、時には問題折衝のために上手く立ち回ることが必要です。
そのためには、人と交流することを厭わず、その場の状況に応じたコミュニケーションを取れる人が向いていると言えます。



確かに、僕が依頼者の立場だったら、親身に話を聞いてくれる人に頼みたいです!



依頼者だけでなく、関係者とコネクションを築くためにも、傾聴力や対応力などの多様なコミュニケーション能力が欠かせません!
文系科目・理系科目の両方の知識がある人
土地家屋調査士に向いている人の特徴の1つ目は「文系科目・理系科目の両方の知識がある人」というものです。
土地家屋調査士に必要な文系科目の知識には、登記申請の際に求められる法律の理解・文書作成能力などがあります。
理系科目の知識としては、図面の作成に必要な空間把握能力や計算力などが挙げられます。
どちらもバランスよくこなせる人が、土地家屋調査士に向いていると言えるでしょう。



土地家屋調査士は、理系出身と文系出身どちらが多いのでしょうか?



理系出身者が多いのかと思いきや、実はどちらも同じくらいの割合です!
土地家屋調査士になってやりがいを感じた人も多数
土地家屋調査士に向いているとはいっても、やはりやりがいを感じることができなければ長続きはしません。
外から「土地家屋調査士はやめとけ」と言われることも多々ありますが、実際に土地家屋調査士として働いている人の声を聞くのが最も説得力があります。
土地家屋調査士になった後に一体どんなやりがいを得ることができるのか、実際に土地家屋調査士として働いている人の声から見ていきましょう!



実際に働いている人はどんなやりがいを感じているんだろう?



やりがいを知って土地家屋調査士になるためのモチベーションを上げていきましょう!
自分の名前が記録に残る
土地家屋調査士のやりがいの1つ目として「自分の名前が記録に残る」といったものがあげられます。
不動産の表題登記は土地家屋調査士にしかできない独占業務であり、作成した登記は、建物が取り壊されたあとに「滅失登記」が提出されるまで残ります。
作成した図面には、作成した土地家屋調査士の名前も記載されます。
自分の名前が後世まで残るというのはとても大きなやりがいと言えますね。



自分の業績が形として残るのは嬉しいですね!



記録に残る分、責任も伴いますが、モチベーションを上げる要因にもなりますね!
トラブルの解決に役立つ
土地家屋調査士のやりがいの2つ目として「トラブルの解決に役立つ」といったものがあげられます。
土地は資産価値が高いので、相続などで土地が引き継がれた際に、境界線を巡って隣人とのトラブルが発生することがあります。
その際に、専門知識を持った土地家屋調査士の測量によって、トラブル解決への道しるべを示すことができます。
トラブルを解決して、双方から感謝されるというのは大きなやりがいですね!



依頼者も関係者も納得できるよう取りまとめてくれる土地家屋調査士は、土地を守るために大切な存在ですね。



時には、弁護士や税理士など他分野の専門家と協力しながら、問題解決のために奮闘しているんですよ!
天災からの復旧の手助けとなる
土地家屋調査士のやりがいの3つ目として「天災からの復旧の手助けとなる」といったものがあげられます。
地震、洪水、津波などの自然災害によって、境界線を失ってしまう場合もあります。
その際に、土地家屋調査士は境界を確認し、土地整備の先駆けとなることができます。
先立って災害からの復興に貢献できることは大きなやりがいですね。



日本は自然災害が多いので、その度に土地家屋調査士に支えられてきたんですね。



これからも災害は増えていく可能性があるので、ますます土地家屋調査士が重要な役割を担うことになりそうですね!
土地家屋調査士やめとけに惑わされるな!就職に向けて全集中しよう
土地家屋調査士に向いている特徴に当てはまっていたあなたは大丈夫です。
土地家屋調査士になっても安心して仕事を獲得し、キャリアを歩んでいけるでしょう!
しかし、土地家屋調査士になるために、そもそも何をどういう風に始めていけばいいのかわからない方もいるのではないでしょうか?
ここでは土地家屋調査士として就職するための方法についてご紹介していきたいと思います!



土地家屋調査士として就職するにはどんな方法が一番近道なのかな?



土地家屋調査士として働くための最も効率的な方法をご紹介していきますね。
まずは土地家屋調査士試験の合格を目指そう
方法の1つ目としては「土地家屋調査士試験に合格する」というものです。
土地家屋調査士になるためには試験に受かることが、条件になってきます。
無資格でも事務所でアルバイトや事務アシスタントとして働くことはできますが、今後独立したり前線に立ってバリバリ活躍していくためには合格が必要ですので、まずは試験に合格することを第一目標としていきましょう!
独学でも合格は可能ですが、限られた時間で高確率で合格を狙うなら通信講座一択なので、合格率を上げたい方は検討してみてください。



土地家屋調査士講座の料金はどれくらいなのかな?



合格圏内レベルにもっていくには約10万円代くらいの料金になります。
特に土地家屋調査士試験を極力一発で受かるのに筆者が一番おすすめしたい講座が『アガルート』です。


『アガルート』は難関資格に特化したオンライン講座であり、土地家屋調査士試験では全国平均の約6.5倍を叩き出すといった実績を持っています。
資格勉強で何から手を付けたらいいかわからなくなることも多いですが、右も左もわからない初学者の方でも、どのような手順で勉強すればいいか道しるべを作ってくれるので迷わずに学習することができますよ。
不安な気持ちではなく、自信をもって合格発表の日を迎え、土地家屋調査士になるためのスムーズな準備ができるように今から合格率を上げられる勉強をしていきましょう!
就職エージェントとの二刀流で就活を進めよう
方法の2つ目としては「就職エージェントとの二刀流で就活を進める」というものです。
ハローワークは求人企業数や就職サポートに限りがあるため、非公開求人情報や就職まで手厚いサポートを受けたい方は就職エージェントと二刀流で就活を進めることをおすすめします。
ハローワークでカバーしきれない部分を就職エージェントで補うことで、より素早く隠れた優良企業に就職できる確率が高くなりますよ!



ハローワークにはなさそうな非公開の優良企業が見つかるエージェントはあるのかな?



非公開の優良企業を多く取り扱うエージェントでは『リクルートエージェント』がおすすめです。


『リクルートエージェント
どうやって土地家屋調査士への就職をすればいいかわからないという方も、実績豊富なプロのエージェントと二人三脚で就職を進められるので、かなり心強い存在になることでしょう。
優良企業へ素早く就職できれば、安定した収入の確保も可能ですし、家族や親せきの喜ぶ顔を見ることだって可能です!
ハローワークにはない非公開求人を見つけて、土地家屋調査士企業への就職できる可能性を高めていきましょう。
【転職支援実績NO.1の大手エージェント】


| 非公開求人数は業界最大の10万件超え | 累計41万人以上のサポート実績※ |
|---|---|
| 書類添削や推薦サポートも充実 | 転職者の8割が利用 |
非公開求人10万件以上!プロから選考対策を伝授
\累計41万人が内定した転職エージェント/
▼ハローワークにはない優良企業も紹介してくれる
土地家屋調査士についてよくある質問
ここでは土地家屋調査士について、よくある質問を共有していきます。
就職をする際の参考にしてみてください!
- 土地家屋調査士の男女比はどれくらいですか?
-
土地家屋調査士の会員数で考えると、男性96%、女性4%と圧倒的に男性が多い職種です。女性も徐々に増えてはいますが、まだまだ少ないのが実情です。
- 土地家屋調査士の受験資格はありますか?
-
特に受験資格はありません。しかし、1級建築士、2級建築士、測量士、測量士補取得者は。測量の試験が免除されます。
- 土地家屋調査士と司法書士の違いは?
-
どちらも同じ登記業務を扱いますが、表題部に関する登記を土地家屋調査士が行い、権利部に関する登記を司法書士が行います。表題部は不動産の物理的状況、権利部は名前の通り所有権などの権利について記録されています。
- 土地家屋調査士が就職・転職できる年齢に制限はあるのでしょうか?
-
そもそも資格が必要な職業であり、独立開業をすれば定年もないので、比較的幅広い年齢で就職・転職は可能です。実際、土地家屋調査士の約4分の3は、50代以上の方が占めています。資格取得を迷っているのであれば、挑戦してみてはいかがでしょうか?
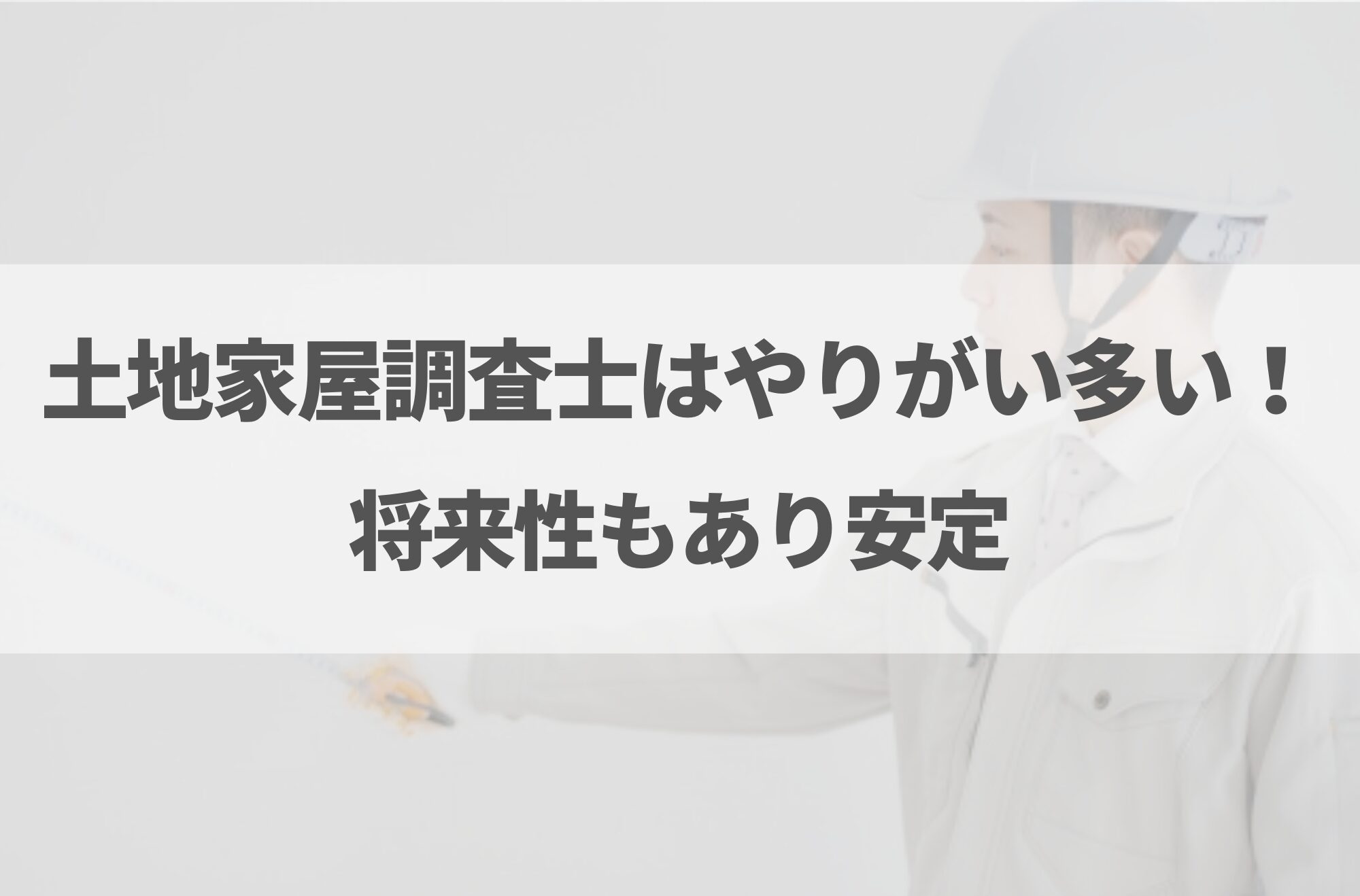
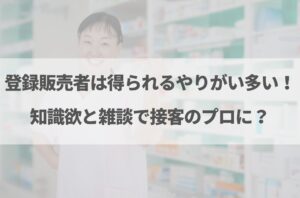
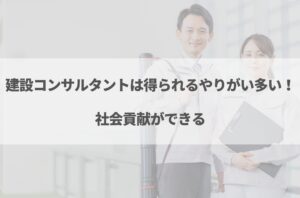
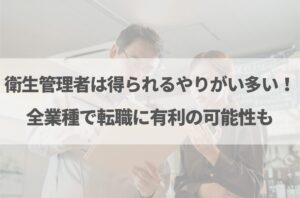
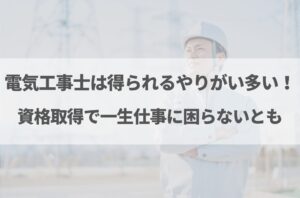
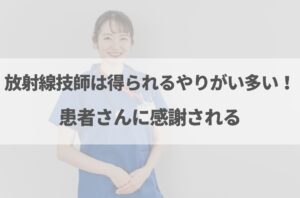



コメント