私たちの暮らしに欠かせない電気を支える電気工事士。
暮らしに必要不可欠な電気に関する工事を支える仕事、手に職をつけたい人や仕事へのやりがいを感じたい人の中には、電気工事士を目指すことを考えている人もいるのではないでしょうか?
世間では、電気工事士はやめとけと言われることもあり、「これから電気工事士になろうと思っていたのに…」「電気工事士への就職に向けて今から準備しようと思っていたけどやめた方がいいのかな」と不安に感じている人もいるかもしれません。
そこで今回は電気工事士はやめとけと言われる理由や、どんな人が電気工事士に向いているのかについてご紹介していきたいと思います!

電気工事士がやめとけと言われる理由やどんな人が活躍しているのか知りたい!



電気工事士になろうか迷っている方は是非参考にしてみてください。
電気工事士のメリットはたくさんある!
そもそも電気工事士になるとどんなメリットがあるのでしょうか?
電気工事士で実際に働いている方の例を参考にどのような良いことがあるのかを一緒に見ていきましょう!



実際に電気工事士で働いている人がどのような点にメリットを感じているかは基調な情報になりそうです!



就職を考えている人にとっては是非とも知りたい情報ですね。
需要が高い
メリットの1つ目は「需要が高い」ということです。
電気工事士は、日常生活に根ざした「電気」の専門家と言えます。
新規の工事の他にも、日々のメンテナンスや修理、また取り換え工事などにも電気工事士は必要となります。
コンセントがきちんと使えること、と言った日々のことから防災・消火設備が問題なく可動することなどのインフラの維持にも無くてはならない仕事の一つです。



今の世の中から電気が無くなったら生活の基盤が崩れちゃいますね!



その通りです。電気は重要なインフラの一つですね。
DIYで出来ることが増える
メリットの2つ目は「DIYで出来ることが増える」ということです。
電気工事士は、国家資格を有することが必要な職業ですが、第二種電気工事士と第一種電気工事士の2種類に分けられます。
第二種電気工事士の資格を取得すると、低圧の電気工事に着手することが出来るようになり、スイッチや照明器具の交換やコンセントの交換などが出来るようになります。
電気工事の材料はホームセンターなどで揃えることが出来るため、自分でコンセントや照明などを取り替えられるようになれば自分で安価にDIYが出来るようになります。



自宅での電気工事の幅が広がりますね!



DIYが流行っている中で、照明やスイッチなどの交換取り付けが出来る人は限られているので需要が多そうですね。
高収入を得られる
メリットの3つ目は「高収入を得られる」ということです。
日本の平均年収は414万円と言われていますが、それに対して電気工事士の平均年収は約507万円と言われています。
電気工事士は、資格や技術が必要な仕事のため、他の職業より収入が高いと言われています。
自身のスキルや経験によって収入増加も見込める仕事です。



特別な技術を持った人は仕事において重宝されそうですね!



やはり手に職と言われる職業なので、他の人との差別化を図りたいところです。
電気工事士はやめとけと言われる理由7選
電気工事士は一生仕事に困らない仕事であるにも関わらず、「電気工事士はやめとけ」と言われることがあります。
電気工事士になりたいと思っていた方にとっては、とても不安になる情報ですよね。
なぜ電気工事士はやめとけと言われるのかについて、世間で言われている理由を見ていきましょう!



一生仕事に困らないのに、なぜ「電気工事士はやめとけ」と言われているんだろう?



それにはいくつか理由があるので一緒に見ていきましょう。
体力の負担が大きいから
やめとけと言われる理由の1つ目としては「体力の負担が大きいから」というものです。
電気工事士は、長時間の立ち仕事に加えて重たい機材を運ぶことが日常的に行われます。
配電板の設置など、重さ10kgを超える機材を持つことも少なくありません。
また、屋外で行う作業も多く、真夏の暑い日や冬の寒い中での作業も珍しくありません。
こうした作業場での重労働が多いことから電気工事士はやめとけと言われているのです。



真夏の暑さに加えて、重たいものを運んで作業となると気が遠くなる作業です…。



そのような中でも作業を行えるだけの体力、そして十分な水分補給も必要となりますね。
狭いところや高いところでの作業があるから
やめとけと言われる理由の2つ目としては「狭いところや高いところでの作業があるから」というものです。
電気工事士の仕事に配線作業がありますが、これらは閉所や高所で行われることも少なくありません。
作業環境を選ぶことは出来ないので、こうしたやり辛い環境においても仕事を全うする、というプレッシャーにさらされます。
高所や閉所での作業も必要なことから電気工事士はやめとけと言われているのです。



危険手当ては出るのでしょうか?



危険手当が出ることもあるようなので、求職サイトでしっかり調べるといいでしょう。
幅広く知識を必要とするから
やめとけと言われる理由の3つ目としては「幅広く知識を必要とするから」というものです。
電気工事士に求められる知識はとても多いです。
電気回路の配線や設計、保安装置の点検など幅広い知識が求められますし、あわせて図面を読み解く能力も必要となってきます。
幅広い知識を必要とすることから電気工事士はやめとけと言われているのです。



学校で学ぶ教科としては理系の知識が必要ですか?



そうですね。数学や物理学といった知識が必要となります。
人材不足による激務になりやすいから
やめとけと言われる理由の4つ目としては「人材不足による激務になりやすいから」というものです。
電気工事士の求職者は減ってきており、また高齢化や退職者も増えているのが現状です。
それでも関係なく仕事の需要はあるので、人手不足に陥ると一人当たりの平均稼働率が上がることは当然、特に夏場のクーラーの設置時期などの繁忙期を迎えると激務に陥りやすい傾向にあります。
今後、ますます人手不足が深刻化すると言われていることから電気工事士はやめとけと言われているのです。



残業も多いのでしょうか?



人手不足、繁忙期と重なるとどうしても残業は増えてきてしまうようです。
命に関わるリスクがあるから
やめとけと言われる理由の5つ目としては「命に関わるリスクがあるから」というものです。
電気工事士は、電気を扱う以上、高電圧という目に見えない危険を伴うときがあります。
段取りが甘かったり、集中して作業を行えないと更にその危険は高まってしまいます。
目に見えない危険を扱うことから電気工事士はやめとけと言われているのです。



高電圧のところで作業している方は本当に大変そうですね…!



そうですね。危険と隣り合わせということを肝に銘じて、一瞬の気の緩みもなく作業に集中すること、また経験を積むことでリスクも回避できるでしょう。
資格取得の難易度が高いから
やめとけと言われる理由の6つ目としては「資格取得の難易度が高いから」というものです。
第二種電気工事士の資格では、一般住宅や店舗といった小規模施設の電気工事に携わることができます。
その他にも、「電気主任技術者」の資格を持っていると発電所や変電所、工場やビルなどの受電設備・配線を扱えるようになるので仕事の幅は広がります。
ただし、この「電気主任技術者」の資格取得合格率は15%という狭き門なのです。
このように資格取得の難易度が高いことから電気工事士はやめとけと言われているのです。



「第二種電気工事士」の資格取得の合格率はどれくらいですか?



こちらは2人に1人が合格の割合と言われています。
見習い時代の年収を低いと感じやすいから
やめとけと言われる理由の7つ目としては「見習い時代の年収を低いと感じやすいから」というものです。
電気工事の仕事はひとり立ちするまで、3〜5年要すると言われています。
それまでが見習いの期間ということになりますが、その間の平均年収は250〜350万程度で、仕事の忙しさに対して割に合わない仕事と感じる人も少なくありません。
見習い時代の年収を割に合わないと感じやすいことから電気工事士はやめとけと言われているのです。



見習い期間は昇給はないのでしょうか?



資格取得をすることで年収アップが臨めます。
そして経験年数とともに年収が上がるとも言われています。
電気工事士をやめた人の理由
電気工事士はやめとけと言われていることもあり、やはり中には実際にやめた人もいることは事実です。
電気工事士として働いていた人がどういった理由でやめていったのかも合わせて見ていきましょう!



実際にやめた人の声を知ることで教訓になりそうですね…



リアルな事情を知ることができるので、参考にしてください。
体力的な負担が大きいから
電気工事士をやめた人の理由の1つ目として「体力的な負担が大きいから」というものがあります。
真夏の炎天下や真冬の寒さの中での作業は、体力的にも精神的にも厳しいものとなります。
重たい機材や工具、資材を運ぶことも少なくないため、腰や肩などに疲れが溜まり、肉体的疲労の蓄積はストレスにもつながりやすく、やめたいと思う人が出てくるのでしょう。



屋外での作業は季節を問わず実施されるわけですね、メンタル維持も大変そうです…。



日頃から体力作りをしていても、暑さ寒さ対策についてはコントロールしきれないところもあり、本当に大変な仕事と言えるでしょう。
危険を伴う作業が多いから
電気工事士をやめた人の理由の2つ目として「危険を伴う仕事が多い」というものがあります。
電気工事士の作業の中で、感電の危険性は排除しきれません。
また、高所や閉所で行う作業も多く、危険を伴うリスクは多い仕事と言えます。
危険を伴う作業ではプレッシャーを感じやすく、それがストレスとなり、耐えきれずに辞めたいと思う人も出てくるようです。



高所や閉所で、さらに天候不良の中での作業となると危険極まりないです。



とても高い集中力や入念な準備、そして作業手順の順守など高い意識が必要となりますね。
給与に不満があるから
電気工事士をやめた人の理由の3つ目として「給与に不満がある」というものがあります。
電気工事士の仕事内容の過酷さや責任の重さ、また長時間労働の割に給与がイマイチ・・・と不満を感じる人が少なくありません。
資格手当が低い、残業代の支払いがないなどの待遇面での不満を感じる人も少なからずいるようで、離職率が上がる原因の一つと言えるでしょう。



給与アップを目指して資格取得出来ても手当が少ないとなるとモチベーションが下がってしまいますね。



そのためにも自分の市場価値を把握して、適切な給与水準を知ることが必要となります。
電気工事士に向いていないのは偶然の可能性も
電気工事士はやめとけと言われてることや、実際に辞めてしまった人もいることは事実ですが、深く心配する必要はありません。
ここでは実際にどのような人が電気工事士になるのをやめておくべきなのか、向いていないのかを確認していきましょう!



電気工事士に向いていない人はどんな特徴があるんだろう?



電気工事士は危険のリスクを伴う仕事なので中には向いていない人もいます。
集中力のない人
電気工事士に向いていない人の特徴1つ目は「集中力のない人」です。
電気工事士は、電気・電圧という目に見えない危険を扱う仕事です。
また、高所や閉所などの難所での作業環境において集中した作業を行えなくなると、自ら危険を招いてしまうことになると言えるでしょう。
目に見えない危険を扱う上に、危険な個所での作業も多いので、集中力のない人は電気工事士に向いていないと言えるでしょう。



集中力の他にも必要な要素はありますか?



集中力と同じくらい注意力が必要です。作業は一人だけで行うものではないので、周りの人を危険に巻き込まないためにも注意力も大切な要素です。
体力がない人
電気工事士に向いていない人の特徴2つ目は「体力がない人」です。
屋外での長時間の作業や重い資材を運ぶ作業も多い仕事の一つ。
また炎天下や真冬の厳しい寒さの中での作業も必要となってきます。
屋外での立ち作業や厳しい暑さ・寒さの中での作業もあるので、体力のない人は電気工事士に向いていないと言えるでしょう。



温暖化の影響で夏の暑さは危険を感じるほどですが、その中でビルの屋上での作業となると、大変な作業なのでしょうね。



会社側もそういった危険性を考えながら作業を実施されると思いますが、やはりそれでも、ある程度の重労働に耐えうるだけの体力は必須となりそうですね。
チームワークの苦手な人
電気工事士に向いていない人の特徴3つ目は「チームワークの苦手な人」です。
電気工事は一人で完結する仕事ではなく、チームで作業することの多い仕事です。
作業現場では、電気工事士の他に設計士や設備業者、建築家などとコミュニケーションをとりながら協力して作業を進める必要があります。
チームの人と効果的なコミュニケーションをとることが求められる現場が多いので、チームワークの苦手な人は電気工事士に向いていないと言えるでしょう。



専門的なメンバーが一堂に介するのですね!



その通り。それぞれの専門家同士で適切な意見交換を行うことで質の高い仕事につながりますね。
電気工事士に向いている人は実はたくさんいる
電気工事士が向いていない人がいることも事実ですが、最低限3つの特徴を持っていれば、電気工事士として活躍していくことは全然可能です。
何も特別なスキルや性格が必要ではありませんので、以下の特徴に当てはまっているあなたは心配せず自信を持って電気工事士になるための準備を進めていきましょう!
- 電気に興味があり、探究心を持って仕事ができる人
- 几帳面で細かい作業の得意な人
- コミュニケーション能力のある人
電気工事士になることを考えている人は是非参考にしてみてください。



自分が電気工事士に向いているかどうか特徴が知りたい!



就職する際に自身に適性がありそうかどうか確かめていきましょう。
電気に興味があり、探究心を持って仕事ができる人
電気工事士に向いている人の特徴の1つ目は「電気に興味があり、探究心を持って仕事ができる人」というものです。
電気工事は、電気回路の設計や配線工事などを扱うため電気に関する幅広い知識と技術が必要になります。
また、電磁気学や電気回路理論などの数学・物理の知識も必要となることから、電気に興味があり、探究心を持って仕事ができる人が向いていると言えるでしょう。



なんだか難しそうな勉強ですね…。



目指す人は数学・物理を強化したいですね。国家試験の筆記試験では計算力も問われるようですよ。
几帳面で細かい作業の得意な人
電気工事士に向いている人の特徴の1つ目は「几帳面で細かい作業の得意な人」というものです。
図面を読み解く力に加えて配線工事の現場などでは、細かい配線を正確に行わなければいけません。
ひとつ配線を間違うと事故につながる恐れもあるので、几帳面で細かい作業の得意な人が向いている仕事と言えます。



根気が必要ですね!



几帳面かつ慎重で根気のいる作業が多くなりますね。
コミュニケーション能力のある人
電気工事士に向いている人の特徴の1つ目は「コミュニケーション能力のある人」というものです。
前述した通りチーム作業が基本の電気工事士、仕事を正確に円滑に行うためにもコミュニケーション能力が必要とされます。
また、危険なものを扱うので、ひとつの伝達ミスが仕事のミスを、そして事故につながりかねないのです。



ちょっとした誤解を生まないためにも、チームの連携をとって正確な仕事を進めていくことが重要なのですね!



指示や説明を的確で正確に伝える能力も必要となりますね。
電気工事士になってやりがいを感じた人も多数
電気工事士に向いているとはいっても、やはりやりがいを感じることができなければ長続きはしません。
外から「電気工事士はやめとけ」と言われることも多々ありますが、実際に電気工事士として働いている人の声を聞くのが最も説得力があります。
電気工事士になった後に一体どんなやりがいを得ることができるのか、実際に電気工事士として働いている人の声から見ていきましょう!



実際に働いている人はどんなやりがいを感じているんだろう?



やりがいを知って電気工事士になるためのモチベーションを上げていきましょう!
社会貢献ができたとき
電気工事士のやりがいの1つ目として「社会貢献ができたとき」といったものがあげられます。
電気工事士が関わる電気設備は、人々の生活にとって欠かせないものです。
社会インフラの安全性の一端を担っていることで社会に貢献していることを実感できると言えるでしょう。
人の生活やこと社会インフラへの貢献を感じられるはとても大きなやりがいと言えますね。



生活に無くてはならない電気の安全性を日々、守ってくれているのですね。



災害時などの緊急時にも頼りになりますね。
資格を取得できた時
電気工事士のやりがいの2つ目として「資格を取得できた時」といったものがあげられます。
電気工事を行うには、電気工事士の資格が必要となりますが、資格を持っていなくても現場に入りながら資格取得を目指すことが出来ます。
一生安定して働くために手に職をつけたいと思う人には、資格の取得は大きなやりがいと言えるでしょう。
資格取得でスキルアップを目指し、それが現場でも貢献できることは大きなやりがいですね!



資格を取得していない人ができる仕事はなんですか?



軽微な工事で、最大電力500KW未満の需要設備と言われています。
チームで仕事をやり終えた時
電気工事士のやりがいの3つ目として「チームで仕事をやり終えた時」といったものがあげられます。
大きな現場などでは、チームで動くこともあります。
チーム全体が一丸となってひとつの仕事をやり遂げた時に大きなやりがいを感じることが出来るでしょう。
チームで成果を出していくことは、大きなやりがいですね。



チーム一丸となって仕事ができることは苦労もあるでしょうけど、達成感も大きいのでしょうね。



一人一人が、日頃からチーム内の意思疎通を図り、モチベーション維持を心がけることで成果に繋がるでしょう。
電気工事士はやめとけに惑わされるな!就職に向けて全集中しよう
電気工事士に向いている人の特徴に当てはまっていたあなたは大丈夫です。
電気工事士になっても安心して働くことができ、キャリアを歩んでいけるでしょう!
しかし、電気工事士になるために、そもそも何をどういう風に始めていけばいいのかわからない方もいるのではないでしょうか?
ここでは電気工事士として就職するための方法についてご紹介していきたいと思います!



電気工事士として就職するにはどんな方法が一番近道なのかな?



電気工事士として働くための最も効率的な方法をご紹介していきますね。
まずは電気工事士試験の合格を目指そう
方法の1つ目としては「電気工事士試験に合格する」というものです。
電気工事士になるためには試験に受かることが、条件になってきます。
無資格でも事務所でアルバイトや事務アシスタントとして働くことはできますが、今後独立したり前線に立ってバリバリ活躍していくためには合格が必要ですので、まずは試験に合格することを第一目標としていきましょう!
独学でも合格は可能ですが、限られた時間で高確率で合格を狙うなら通信講座一択なので、合格率を上げたい方は検討してみてください。



電気工事士講座の料金はどれくらいなのかな?



合格圏内レベルにもっていくには約10万円代くらいの料金になります。
特に電気工事士試験を極力一発で受かるのに筆者が一番おすすめしたい講座が『アガルート』です。


『アガルート』は難関資格に特化したオンライン講座であり、電気工事士試験では<アガルートが持つ実績を書いてください>といった実績を持っています。
資格勉強で何から手を付けたらいいかわからなくなることも多いですが、右も左もわからない初学者の方でも、どのような手順で勉強すればいいか道しるべを作ってくれるので迷わずに学習することができますよ。
不安な気持ちではなく、自信をもって合格発表の日を迎え、電気工事士になるためのスムーズな準備ができるように今から合格率を上げられる勉強をしていきましょう!
就職エージェントとの二刀流で就活を進めよう
方法の2つ目としては「就職エージェントとの二刀流で就活を進める」というものです。
ハローワークは求人企業数や就職サポートに限りがあるため、非公開求人情報や就職まで手厚いサポートを受けたい方は就職エージェントと二刀流で就活を進めることをおすすめします。
ハローワークでカバーしきれない部分を就職エージェントで補うことで、より素早く隠れた優良企業に就職できる確率が高くなりますよ!



ハローワークにはなさそうな非公開の優良企業が見つかるエージェントはあるのかな?



非公開の優良企業を多く取り扱うエージェントでは『リクルートエージェント』がおすすめです。


『リクルートエージェント
どうやって電気工事士への就職をすればいいかわからないという方も、実績豊富なプロのエージェントと二人三脚で就職を進められるので、かなり心強い存在になることでしょう。
優良企業へ素早く就職できれば、安定した収入の確保も可能ですし、家族や親せきの喜ぶ顔を見ることだって可能です!
ハローワークにはない非公開求人を見つけて、電気工事士企業への就職できる可能性を高めていきましょう。
【転職支援実績NO.1の大手エージェント】


| 非公開求人数は業界最大の10万件超え | 累計41万人以上のサポート実績※ |
|---|---|
| 書類添削や推薦サポートも充実 | 転職者の8割が利用 |
非公開求人10万件以上!プロから選考対策を伝授
\累計41万人が内定した転職エージェント/
▼ハローワークにはない優良企業も紹介してくれる
電気工事士についてよくある質問
ここでは電気工事士について、よくある質問を共有していきます。
就職をする際の参考にしてみてください!
- 電気工事士資格試験の難易度は?
-
第一種の合格率は学科試験は40%程度、技能試験は60%程度と言われています。
第二種の方では学科試験60%程度、技能試験は70%程度と難易度が高くなります。
- 電気工事士の男女比率はどんな感じでしょうか。
-
圧倒的に男性が多くなります。
2022年賃金構造基本統計調査特別集計によると男性が約98%、女性が約2%とのことです。
- 電気工事士の仕事は危険ですか?
-
漏電や感電といった危険は隣り合わせです。
そのためにも電気の知識を学び理解して、正しく扱うことで危険から身を守ることが出来ます。
- 電気工事士の仕事に夜勤はありますか?
-
現場によってはあります。
一般的に、午後10時から午前6時までの時間帯が普通です。
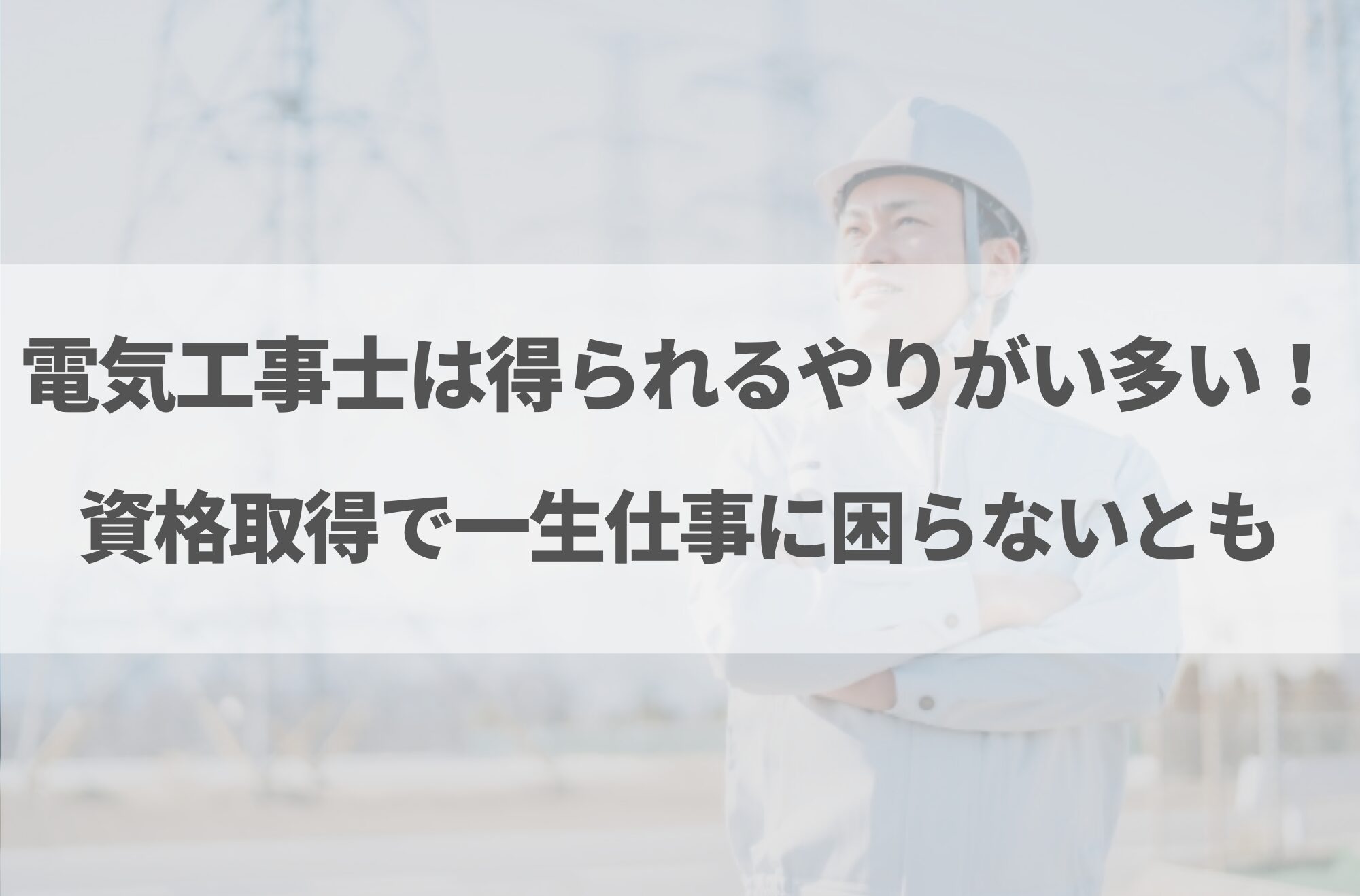
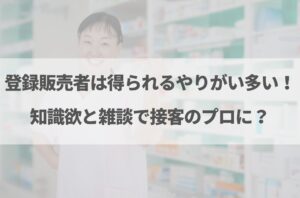
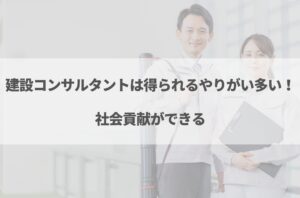
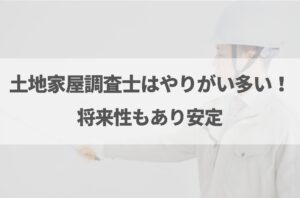
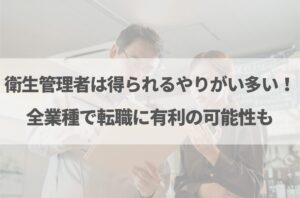
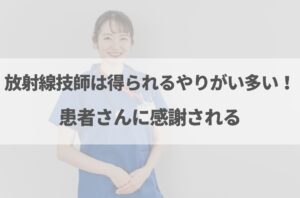



コメント